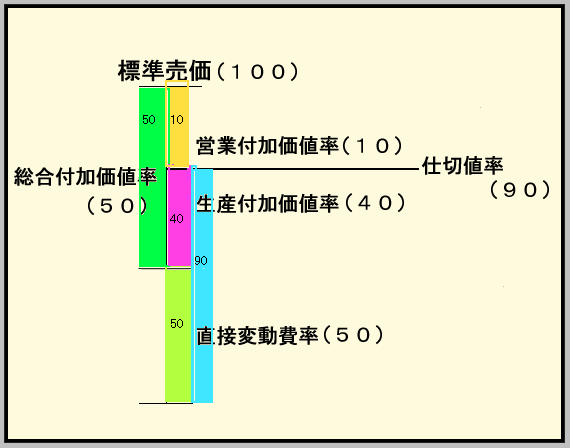一般的に使われている振替価格は、取り引きの事後会計処理として性格が強いのです。
この方法には、市価基準、売価還元方式等かありますり、会社の実態により異なりますが、
組織内に業績中心の精神が強ければ強いほど振替価格の利害関係に敏感になります。
それだけに振替価格の決定手続きを誤り、当事者の理解と納得が得られないと、
かえってさまざまなデメリットが生じます。
OMCの仕切値制度は、これとは全く異なり、生産と販売(営業)部門間に政策的に事前に設定し、以後この設定線からそれぞれが“いかに良化したか”のアクションの拠点にするものです。
仕切額の高い、低いのの問題ではなく、
その線を境に、営業はいかに営業付加価値を高めたか
生産はいかに生産付加価値を高めたかの拠点となるものです。
これにより、売価に強い営業、コストに強い生産を実現させ、業績アップを計る必須のシステムです。

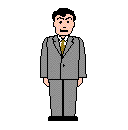
 直接変動費を削減したか
直接変動費を削減したか